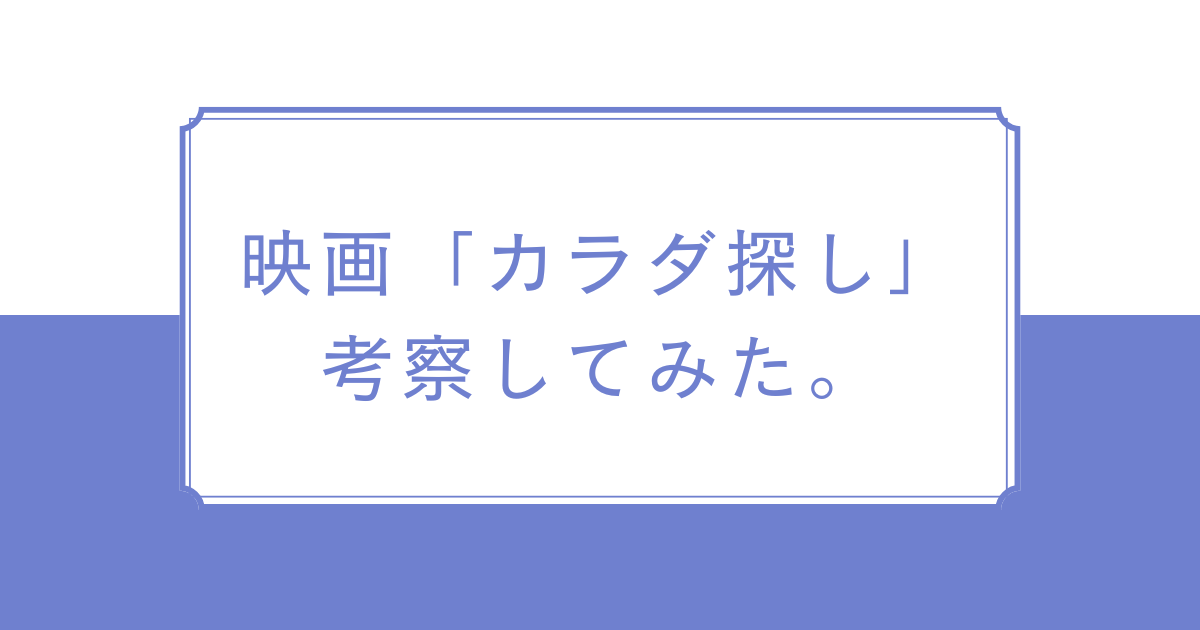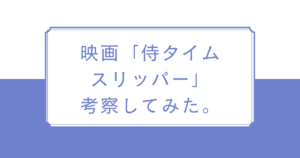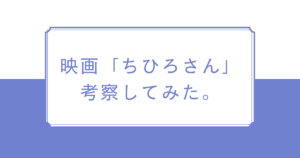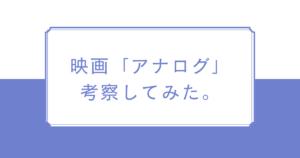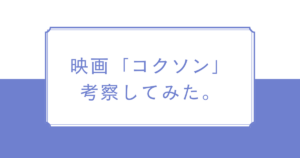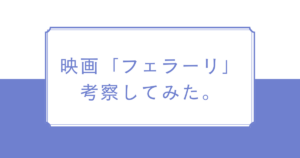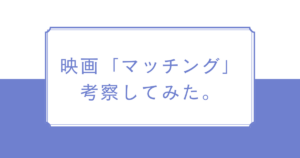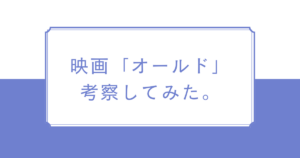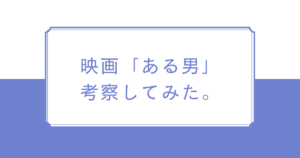映画『カラダ探し』は、ホラーと青春ドラマが交錯する作品であり、視覚的な恐怖描写と複雑なストーリーが魅力です。
物語の中で繰り返されるループと、それに伴う登場人物たちの変化が観る者に深い印象を与えます。
本記事では、『カラダ探し』の主要な考察ポイントをいくつか挙げて、物語の核心に迫っていきます。
考察① 明日香の「赤い人」とは何か
映画を通して、明日香を追い詰める存在「赤い人」が物語の重要な要素となります。
この「赤い人」は、ただの怪物ではなく、物語の中で複雑な意味を持つキャラクターとして描かれています。
まず、明日香がカラダ探しのルールに巻き込まれる過程で赤い人が登場し、彼女の心に強い影響を与えていきます。
考察の一つとして、赤い人が「明日香自身である可能性」が挙げられます。
エンドクレジット後のシーンで、明日香が小さい頃に体験した出来事が振り返られます。
その中で、赤い人の正体が徐々に明らかになります。
実は、赤い人が明日香自身であり、彼女が体験した一連の出来事が全て彼女の妄想である可能性が示唆されます。
つまり、明日香が抱えていた心の闇や未解決の感情が「赤い人」として具現化し、物語を通じて明日香を試していたとも考えられるのです。
考察② 「カラダ探し」のルールとその背後にある意味
映画で描かれる「カラダ探し」のルールは、登場人物たちが直面する試練の中心となります。
これらのルールは単なるホラーゲームのように見えますが、実際には深い心理的な意味が込められているのではないかと考えられます。
「カラダ探し」のルールの中には、「死んだら永遠に同じ日を繰り返す」というものがあります。
このルールが示唆するのは、物語の登場人物たちが過去の罪や後悔から逃れることなく、繰り返し同じ状況に直面することを意味している可能性が高いです。
明日香をはじめとする登場人物たちは、カラダ探しを通じて過去の自分と向き合い、最終的にはそれを乗り越えなければならないというテーマが込められていると解釈できます。
また、ルールに従って体を探し集める過程は、チームワークや友情を試す要素でもあります。
明日香が孤立していた状態から、仲間たちとの絆を深めていく過程が描かれることで、物語の中での成長や変化が際立ちます。
考察③ 明日香の記憶とループの終わり
物語のクライマックスでは、明日香がループを脱するために「カラダ探し」を終わらせる決断を下します。
この時、明日香は友情や恋愛を経験し、成長しますが、そのすべてが消えてしまうという悲劇が待っています。
7つ目のルールによって、記憶が消えることで、明日香は再び何も覚えていない状態から新しい日々を始めることになります。
このラストシーンの考察としては、明日香が成し遂げた友情や恋愛が消えることに対する葛藤が大きなテーマとなっている点です。
彼女はループから抜け出したいという強い願望を持ちながらも、失われたものに対する寂しさと向き合わせられます。
この複雑な感情の描写は、現実の人生においても多くの人が経験する「失われたものの痛み」に通じる部分があり、観る者に強い共感を呼び起こします。
また、ラストシーンで明日香が再び高広と出会うことで、一見ハッピーエンドのように見えますが、実際にはその記憶の消失が示すように、物語は循環し続けている可能性を残しています。
この「終わりのないループ」は、登場人物たちが直面した恐怖や成長、そして失われたものを象徴していると言えるでしょう。
まとめ
映画『カラダ探し』は、単なるホラー映画にとどまらず、深い心理的なテーマやキャラクターの成長を描いた作品です。
明日香の「赤い人」とは彼女自身の内面的な葛藤を象徴する存在であり、カラダ探しのルールは登場人物たちが過去と向き合い、成長するための試練として機能しています。
ラストシーンにおける記憶の消失というテーマも、物語全体に深い意味を持たせる要素となっており、観る者に強い印象を与えます。
この映画は、ホラーと青春ドラマの融合が巧妙に描かれており、物語の中で何度も繰り返されるループを通じて、登場人物たちがどのように変わり、どのように向き合っていくのかが見どころです。