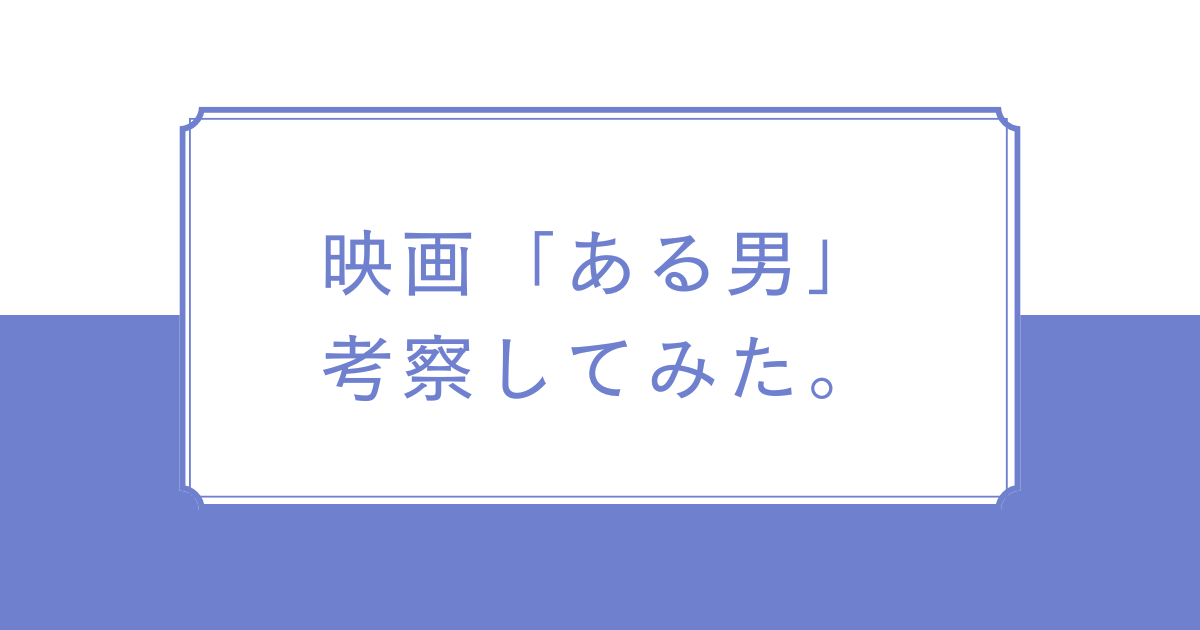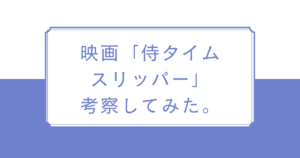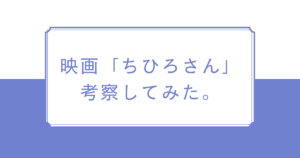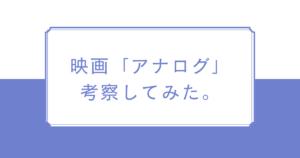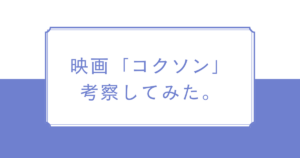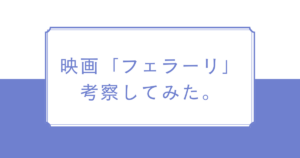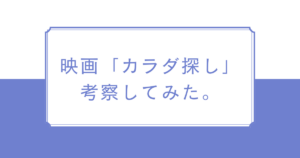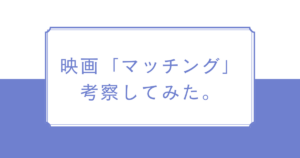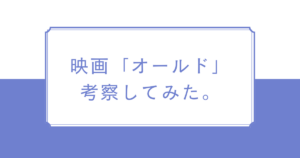映画『ある男』は、平野啓一郎の同名小説を基にした作品で、ミステリーとドラマが交錯する複雑な内容が描かれています。
主演には妻夫木聡、窪田正孝、安藤サクラと豪華なキャストが揃い、その演技力が光る作品です。
本作は、夫が愛したはずの全く別人だったという衝撃的な設定を軸に、人物の過去と現在、そしてそれが現代社会でどのように影響を与えるのかを描いています。
今回は、この映画のテーマやラストシーンを深掘りし、映画が何を伝えようとしているのかを考察していきます。
考察①:差別と血統の問題
本作が描いている最も重要なテーマの一つは、「血統」や「差別」に対する問題です。
映画の中で、在日コリアンの弁護士城戸は、自分がどこから来たのか、どのような背景を持っているのかということで差別を受けます。
城戸は、名前や顔、そして生まれ持った背景だけで他者から評価される社会の現実に苦しみながらも、良い弁護士であろうと努めています。
また、映画では、「ある男X」と呼ばれる人物が重要な役割を果たします。
Xの正体を追い求める過程で、彼の過去や戸籍が変わったことが社会的な意味を持つことに気づかされます。
血統というものが、いかに個人を縛り、時に不当な評価を受ける原因になるのかを描いており、非常に社会的な問題を浮き彫りにしています。
考察②:過去と現在の自己認識
『ある男』における大きなテーマの一つは、「過去と現在」という二つの時間軸の関係です。
物語の中心には、夫を亡くした里枝がいますが、彼女が愛した夫が全く別人だったことを知ることになります。
この「別人」という事実は、里枝にとって自身の過去と現在をどう位置づけるかという大きな問題を突きつけます。
夫の正体が明らかになることで、里枝は自分がどれだけ過去に依存していたのか、そしてそれにどう向き合うべきなのかを問われることになります。
しかし、映画が示唆するのは、過去の全てを知ることが必ずしも幸せに繋がるわけではないということです。
大切なのは今、そして未来であり、過去を乗り越えて新たな一歩を踏み出す勇気を持つことの重要性を強調しているように感じました。
考察③:ラストシーンの謎と解釈
映画『ある男』のラストシーンは非常に謎めいており、観客に大きな余韻を残します。
特に注目すべきは、妻夫木聡が演じる城戸がバーで別の男性と語るシーンです。
ここで城戸は、谷口大祐という別の名前で過去の人生を語り始めます。
この場面が示唆するのは、城戸が戸籍を交換して新しい人生を歩むのか、それとも自分の過去を背負って生き続けるのかという選択です。
ここで提示されるのは、名前や血統を変えることの意味についての深い問いかけです。
城戸が実際に戸籍交換をして新たな人生を歩み始めたのか、それとも単に自分を疑似的に谷口大祐に見立てて生きているのかは、観客に委ねられています。
この曖昧さが、映画全体のテーマである「自己認識」と「過去の解釈」に繋がる重要な要素となっています。
まとめ
映画『ある男』は、ミステリー的な要素とドラマ的な要素が融合した作品であり、社会的なテーマや人間関係に対する鋭い視点が描かれています。
本作の大きなテーマは「血統」「差別」「過去と現在」の関係であり、それを通して現代社会における人々の苦悩と葛藤を描き出しています。
また、ラストシーンの曖昧さが映画のメッセージをより深く印象づけ、観客に自らの解釈を促します。
全体的に、ドラマとしての要素が強いものの、ミステリーを期待して観た人々にとっては少し物足りなさを感じる部分もあったかもしれません。
しかし、映画の本質的なテーマに対して深い洞察を得ることができる、非常に考えさせられる作品だと言えるでしょう。