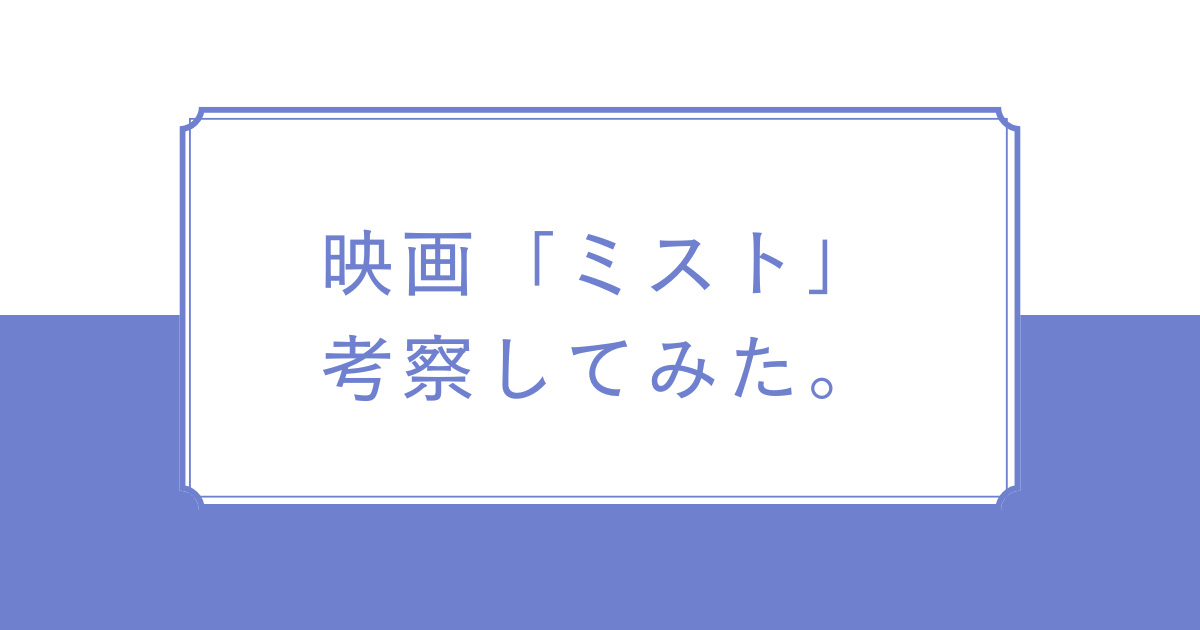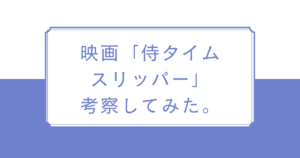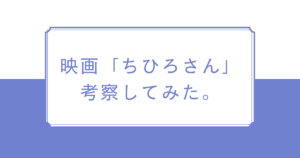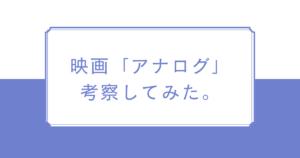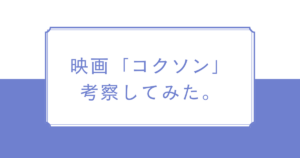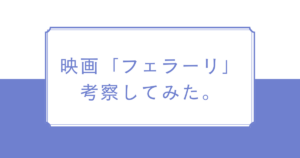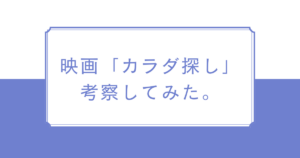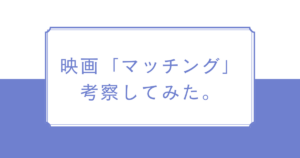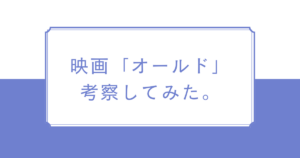映画『ミスト』(2007年)は、スティーヴン・キングの短編小説を基にした衝撃的なパニック映画です。
霧に覆われた町で、超自然的な怪物たちに囲まれた人々のサバイバル劇を描いています。
本作はその衝撃的なラストシーンをはじめ、深いテーマ性が話題となり、観客に強い印象を与えました。
今回は、映画『ミスト』の考察を3つの視点からまとめていきます。
考察① 思想の対立が生む悲劇
映画の中で最も印象的なテーマは、「人間同士の思想の対立がもたらす悲劇」です。
霧の中で閉じ込められた人々は、それぞれ異なる解釈を持ちながら行動します。
一方は冷静に事態を受け入れ、外部からの救助を待つべきだと考えます。
他方では、宗教的な信念を持つ人物が、自分の解釈に基づいて周囲を煽動し、犠牲者を生み出します。
最終的に、怪物による死よりも人間同士の対立による死者の方が多くなるという事実が、観客に強い衝撃を与えます。
例えば、最初に命を落とした若者は、無謀にも霧の中に飛び出していきます。
彼の行動は、他の人々に影響を与え、結果的に自分たちが置かれた状況を悪化させます。
また、宗教的狂信者の存在が、事態をさらに悪化させる要因となり、人々は互いに対立し、無駄な命を失うことになります。
このように、思想の違いによる分裂が、現実的な危機を乗り越えるための団結を妨げ、悲劇を招いてしまうことが本作の大きなテーマとなっています。
考察② 意味付けと人間の本能
『ミスト』は、人間の本能的な「意味付け」の欲求を描いています。
人間は、どんな状況でも意味や法則性を見出そうとする生き物です。
霧に包まれたスーパーでの混乱において、登場人物たちは事象に意味を見出そうとします。
宗教的な解釈を持ち込んだり、必死に自衛の手段を講じたりすることで、彼らは不安を和らげようとします。
このような行動は、時に人々を対立させ、無駄な犠牲を生む原因となります。
例えば、主人公が冷静に状況を分析しようとしても、宗教原理主義者や自己中心的な人物たちは、その解釈に固執し、集団内で強い対立を生みます。
さらに、霧という不可解な現象に直面したことで、人々は本能的に「意味」を求め、無理にでも納得しようとするのです。
しかし、実際にはその意味が全くの偶然や無意味なものであったとしても、登場人物たちはそれにしがみついてしまいます。
この描写は、人間の心理的なメカニズムを鋭く突き詰めたものだと言えるでしょう。
考察③ 運命の皮肉とラストシーン
映画のラストシーンでは、主人公が大きな決断を下す場面が描かれます。
彼が「絶望的な状況だ」と判断し、集団自殺を選んだその瞬間、運命の皮肉が待ち受けていました。
ラストでは、主人公が命を落とすことなく生き残る女性と再会しますが、このシーンには強烈な皮肉が込められています。
彼が絶望的な状況に陥り、最も重要な選択をしたにもかかわらず、その決断は「偶然」によるものでしかなかったことが明かされます。
この点が、映画を観た人々にとって強烈な衝撃を与えた理由の一つです。
人間が自らの解釈に基づいて行動する一方で、その結果が無意味であったことが描かれることで、観客は「人間の思い込みや行動が、時に運命に翻弄されること」を強く実感させられます。
まとめ
映画『ミスト』は、単なるパニック映画にとどまらず、深いテーマを持った作品です。
思想の対立が招く悲劇や、人間の本能的な「意味付け」に対する欲求が、登場人物たちの運命を大きく左右します。
そして、ラストシーンで描かれる皮肉な運命が、この映画のテーマをより深く印象づけています。
本作は、観る人に強い感情的な影響を与えると同時に、人間の本質についても鋭い洞察を与えてくれる映画です。