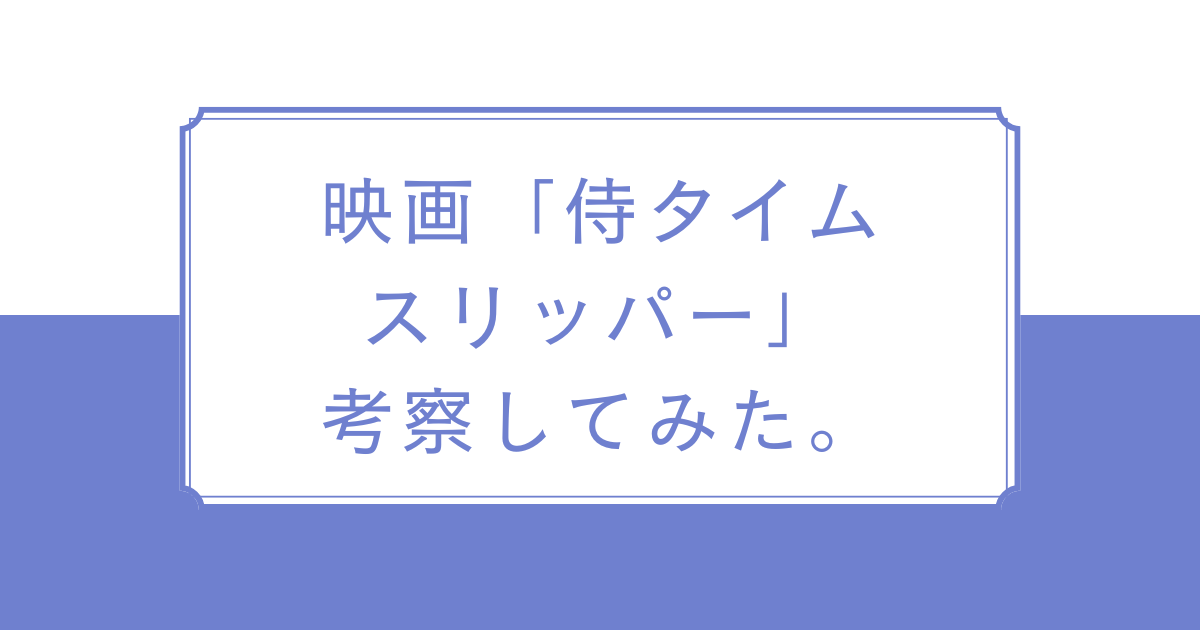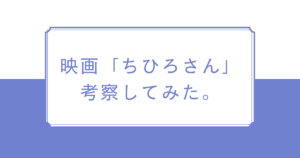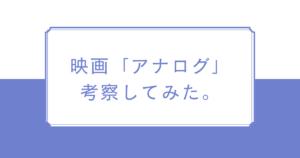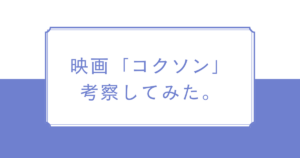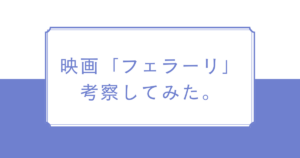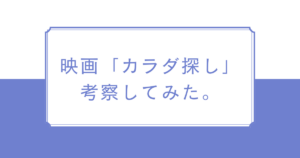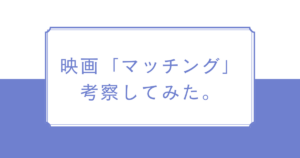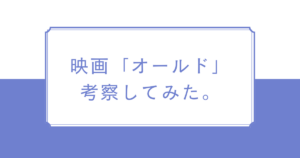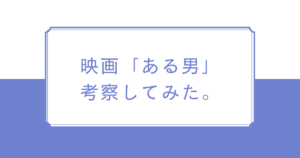映画「侍タイムスリッパー」は、タイムスリップをテーマにした斬新な時代劇で、観客に強い印象を残す作品です。
今回はその魅力を深掘りし、映画のストーリー、制作背景、そしてテーマについて考察します。
考察① 映画愛が溢れる作品
「侍タイムスリッパー」を観ると、映画制作に対する深い愛情が感じられます。
安田監督の映画に対する情熱が、作品全体に息づいています。
特に、映画内で時代劇のセットを舞台にして現代にタイムスリップするシーンでは、映画愛が溢れる演出が目を引きます。
具体的に言うと、主人公の高坂新左衛門が時代劇の撮影所で迷い込んだシーンでは、映画のセットに違和感なく溶け込んでしまう描写が印象的です。
時代劇のアクションが繰り返される中、映画制作の裏側を垣間見ることができ、その繊細な描写が観客に強い印象を与えます。
さらに、ニューシネマパラダイスや「カメラを止めるな!」といった映画作品にも見られる映画愛が、この作品にも息づいており、映画ファンにとってはその共鳴が心地よいものとなっています。
考察② 映画制作の裏側と監督のこだわり
「侍タイムスリッパー」のもう一つの特徴は、安田監督の映画制作に対するこだわりが随所に見られることです。
彼はスクリプターも兼任し、全11役を一手にこなすという異例の手法を取りました。
特に、自主制作映画としては画期的な試みと言えるでしょう。
制作においては、スタッフの人数が限られていたにも関わらず、絵作りには一切手を抜かず、きめ細やかな映像美を追求しました。
特に、タイムスリップの瞬間における美しい京都の街並みの描写や、侍が踏切りの前で立ちすくむシーンは、映画ファンにとって見逃せない場面です。
こうした丁寧な映像作りは、安田監督の「映画を作る」という姿勢が強く表れています。
また、映画の中で「ご飯」や「切られ役」といったテーマが織り交ぜられ、映画の細部にわたって安田監督の深い思いが込められていることが伝わります。
彼の映画作りに対する情熱とこだわりが、映画全体を一貫したテーマでまとめあげているのです。
考察③ 物語の構造と時代劇の再評価
物語が進むにつれて、「侍タイムスリッパー」は単なるコメディではなく、シリアスな展開に突入します。
タイムスリップした侍が現代に迷い込み、切られ役として活躍する中で、次第にその背後に隠された深いドラマが明らかになります。
特に注目すべきは、物語が後半に進むにつれて、戦国時代の侍たちの誇りや使命感が浮き彫りになる点です。
最初は軽いコメディタッチで進行していた物語が、先輩俳優の登場をきっかけにシリアスな方向へと変化し、最後には真剣を使った緊迫した戦いが繰り広げられます。
このように、物語が段階的に変化する点は、「君の名は。」や「時をかける少女」といった作品の構造に似ています。
また、時代劇というジャンルが抱える危機感にも触れています。
現代において、時代劇の人気は低迷していますが、安田監督はその魅力を再評価し、作品を通じて時代劇の未来を切り開こうとしています。
彼の意図は、単なる懐古主義に留まらず、現代の観客にも通じる新しい時代劇の形を提示することにあります。
まとめ
映画「侍タイムスリッパー」は、単なるタイムスリップを描いたエンターテイメントに留まらず、映画制作への情熱や時代劇の再評価という深いテーマを掘り下げた作品です。
安田監督のこだわり抜かれた映像作りと物語の展開が観客を引き込み、映画愛に溢れた作品に仕上がっています。
時代劇や映画制作の現場の裏側を知ることで、作品の深さがより一層感じられます。
今後もこの映画がどのように広がっていくのか、注目が集まることでしょう。